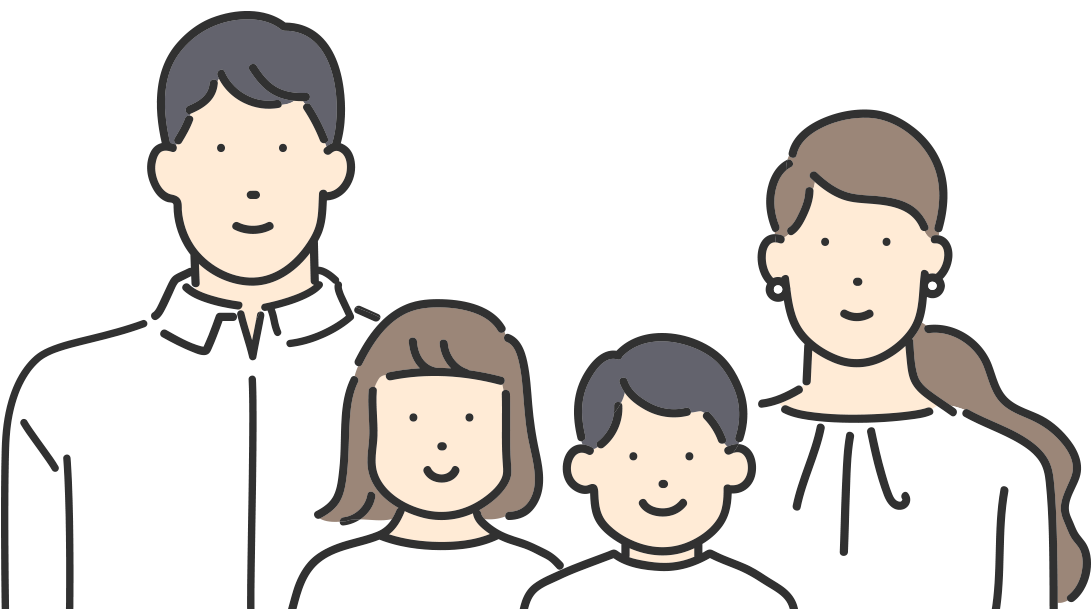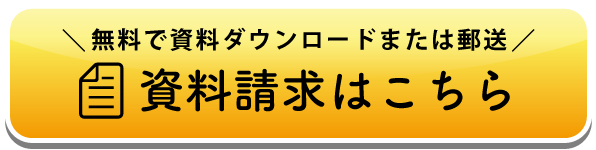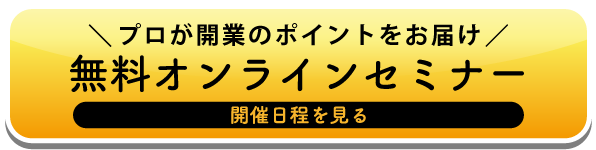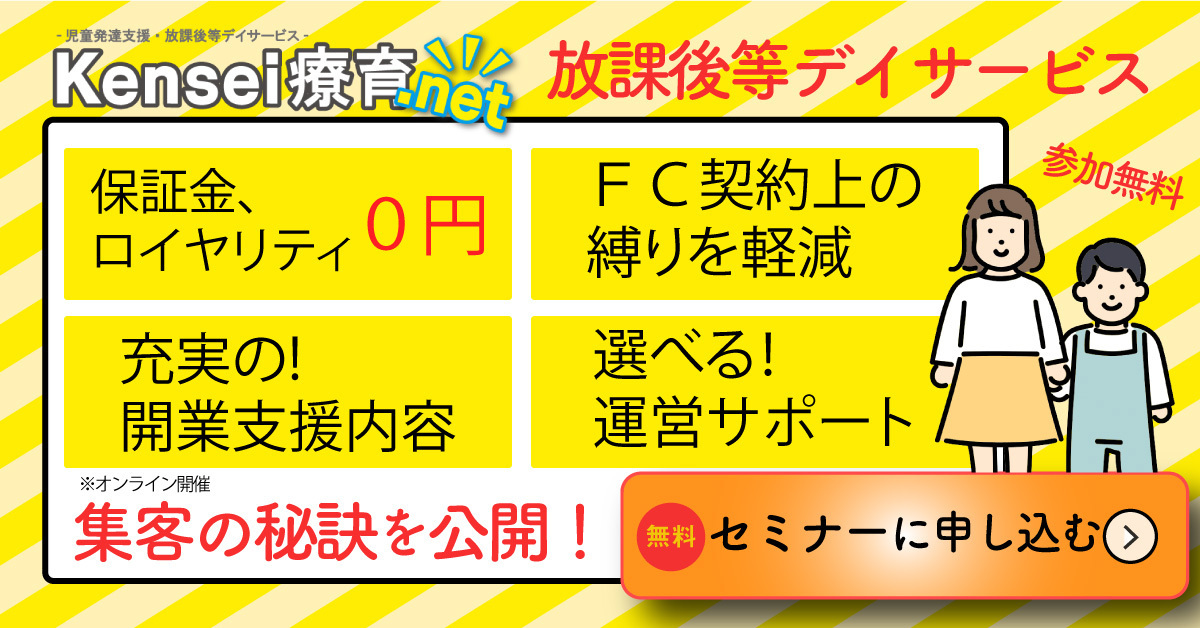放課後等デイサービス 5領域とは?その意味・目的・活かし方をやさしく解説

放課後等デイサービスの支援において、「5領域」という言葉を聞いたことがある保護者や支援者の方も多いのではないでしょうか。
この「5領域」は、子どもの成長を支えるための大切な指標であり、支援の現場で幅広く活用されています。
この記事では、「放課後等デイサービス 5領域」とは何か、その意味や目的、実際にどう活かされているのかを、やさしい言葉でわかりやすく解説します。
放課後等デイサービス 5領域 とは何か?基本をやさしく解説
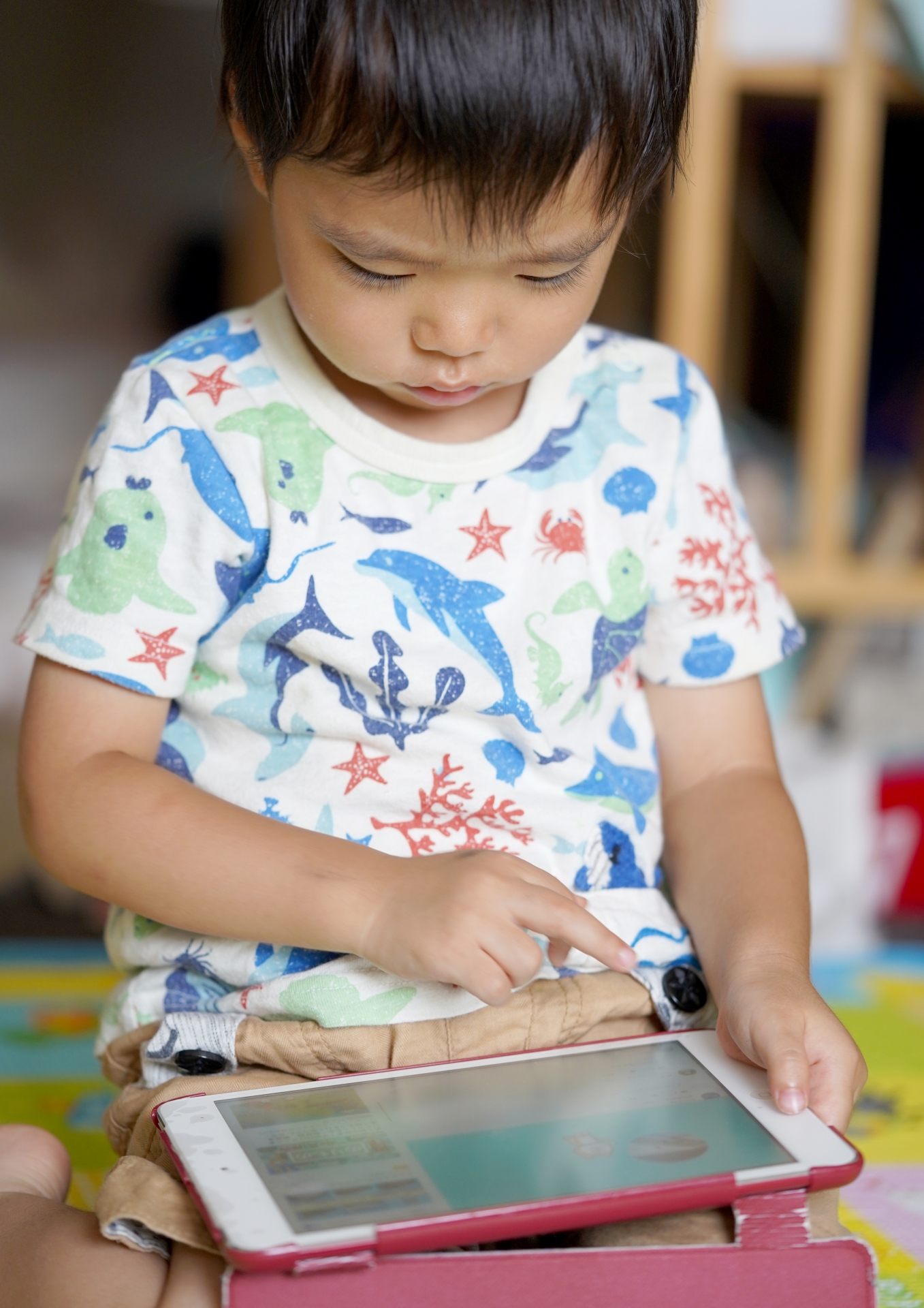
厚生労働省(現:こども家庭庁)が示した5つの発達領域を指す
「5領域」とは、国の障害児通所支援ガイドラインで示される「本人支援の5領域」のことで、子どもたちが育つ上で大切な力を5つの視点から捉えています。
これらは「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つです。
なお、特別支援教育で用いられる「自立活動」(6区分)とは別の枠組みです。
放課後等デイサービスの支援内容も、この5つの観点から整理されています。
療育の土台として義務化されている
この5領域は、国のガイドラインで活用が求められており、放課後等デイサービスや児童発達支援事業所などで個別支援計画や日常活動の設計に広く使われています。
2024年(令和6年)4月1日以降は、5領域との関連性を明確にした「支援プログラム」を作成・公表することが求められ、対応していない場合は2025年(令和7年)4月1日以降は未公表減算の対象となります。
施設ごとに活動内容は異なっていても、この5つの視点に基づいて構成されているのが一般的です。
そのため、施設を移動した場合でも、支援の継続性が保たれやすくなります。
子どもの成長をバランスよく支えるための指標
子どもはそれぞれに得意・不得意があり、発達にも偏りが見られることがあります。
5領域という枠組みを使うことで、特定の分野だけに偏らず、バランスよく支援することが可能になります。
たとえば、言葉がうまく使えない子どもに対して、言語だけでなく、感覚や行動など他の領域からアプローチすることも重要です。
このように、5領域は子どもの成長を包括的にサポートするための重要な指針となっています。
放課後等デイサービス 5領域はなぜ重要なのか?その目的を知ろう
発達に偏りがある子どもへの適切な支援ができるから
発達に遅れや偏りがある子どもは、それぞれ違った課題を抱えています。
5領域を使うことで、その子の状態を正確に把握し、必要な支援を計画することができます。
例えば、行動のコントロールが難しい子には「認知・行動」、言葉の理解が苦手な子には「言語・コミュニケーション」を重視した支援ができます。
このように、一人一人が持つ課題に合わせた支援がしやすくなるのです。
保護者と施設スタッフが共通認識を持ちやすくなるから
支援を進める上で、保護者との連携はとても大切です。
5領域の視点があれば、「どの部分を支援しているのか」「何を目指しているのか」が共有しやすくなります。
結果として、保護者が家庭でできる関わり方にもヒントを得やすくなります。
共通認識があることで、支援の一体感も生まれやすくなります。
支援内容の質を高めるためのガイドになるから
施設での支援活動が感覚的・場当たり的にならないよう、5領域という指針を使うことで、計画的かつ効果的な支援が実現できます。
スタッフは「どの力を育てたいのか」を意識しながら活動を設計します。
活動後の振り返りや評価にも活用でき、支援の質の向上につながります。
放課後等デイサービス 5領域 とはどのような内容なのか?各領域の紹介

健康・生活:健康を維持し、身支度や食事など生活習慣の力を育てる
「健康・生活」領域では、健康を維持し、身の回りのことを自分でできる力を育てる支援が行われます。
例えば、着替え、歯みがき、手洗い、排せつ、食事など、日常生活に欠かせない基本的な動作が含まれます。
生活のリズムを整え、安心して過ごせる基盤をつくることが目的です。
自己管理能力や安全に対する意識も、この領域に含まれます。
運動・感覚:体を動かす力や感覚を育てる
この領域では、体のバランス感覚や筋力、手先の器用さなど、運動能力の発達を促す活動が中心です。
また、音や光、触った感覚などを心地よく感じる力=感覚統合の支援も含まれます。
運動療育やリズム遊び、感覚遊びなどの活動が行われることが多いです。
この領域が育つことで、他の領域の土台も安定しやすくなります。
認知・行動:考える力や集中力、行動のコントロールを育てる
「認知・行動」では、物事を理解したり、自分で考えて行動したりする力に焦点を当てます。
注意の持続や指示の理解、問題解決の力などがこの領域に含まれます。
ルールの理解や衝動的な行動を抑えるトレーニングも行います。
学習支援とも関係が深く、学校生活との接続にもつながります。
言語・コミュニケーション:言葉の理解ややりとりの力を育てる
この領域では、人と関わるために必要な「伝える・聞く・理解する」力を育てます。
単語や文の理解、質問への返答、感情の表現など、言葉のやりとり全般が対象です。
会話練習や絵カードを使った活動が多く行われます。
言葉だけでなく、表情やジェスチャーなど非言語のコミュニケーションも含まれます。
人間関係・社会性:友だちとの関係づくりや社会のルールを学ぶ
この領域では、集団生活の中で人と関わる力を育てます。
友だちと遊ぶ、順番を守る、感情をコントロールするなど、社会で生きていくために必要な力です。
ソーシャルスキルトレーニング(SST)などがよく使われます。
自分と他人の違いを認める気持ちを育てることも大切なポイントです。
放課後等デイサービス 5領域 とは具体的にどう活かされているのか?支援の現場から
個別支援計画に5領域を基にした目標を設定している
放課後等デイサービスでは、利用者ごとに「個別支援計画」を作成します。
その際、5領域に対応した目標を設定するのが一般的です。
たとえば、「健康・生活」であれば「自分で靴を履く」「食事の前に手を洗う」などの具体的な目標になります。
成長の様子を記録・評価する際にも、5領域が基準になります。
日常活動(例:SSTや運動療育)に5領域の考え方が組み込まれている
日々の活動も、5領域のいずれかに結びつけられています。
例えば、SSTは「人間関係・社会性」、運動療育は「運動・感覚」、絵本の読み聞かせは「言語・コミュニケーション」といった具合です。
活動の目的を明確にしやすく、支援の効果を高めることにつながります。
子どもたちも、楽しみながらさまざまな力を自然と身につけていきます。
スタッフの評価や振り返りにも活用されている
スタッフが支援を振り返るときも、5領域は重要な基準になります。
「今日は運動・感覚の活動が中心だった」「人間関係・社会性の場面でトラブルが起きた」など、記録や報告に一貫性が出るため、チームでの連携が取りやすくなります。
新人職員の指導にも役立ち、支援全体の質の向上に貢献しています。
放課後等デイサービス 5領域 とは保護者にとって何を意味するのか?理解するメリット

支援の内容や目的が明確にわかるようになる
「なぜこの活動をしているのか?」が明確に説明できるのが5領域のよさです。
たとえば、紙芝居を読む時間が「言語・コミュニケーション」の支援だと理解すれば、支援の価値がより納得できます。
保護者が支援の背景を理解することで、不安や誤解も減り、信頼関係が深まります。
目的が見えることで、家庭での取り組みとの連携もしやすくなります。
家庭での接し方の参考にしやすくなる
5領域を知ることで、家庭でも同じ視点で子どもを見守ることができます。
「言葉のやりとりを増やしてみよう」「お手伝いで生活スキルを育てよう」といった工夫がしやすくなります。
施設と家庭が同じ目標に向かって支援できることは、子どもの成長にとってとても大切です。
日常の関わりも、より意味のある時間に変わるでしょう。
支援の進み具合を一緒に確認できるようになる
子どもの成長を把握するためにも、5領域の視点は役立ちます。
施設からの報告や面談でも、「○○領域での変化」といった形で成果が見えるため、成長を実感しやすくなります。
「以前はできなかったことが、今はできるようになっている」ことを具体的に伝えてもらえると安心ですよね。
支援の評価や今後の方向性も、保護者と一緒に話し合いやすくなります。
まとめ|放課後等デイサービス 5領域 とは何かを正しく理解しよう
5領域は子どもの発達支援の基本となる考え方
「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」の5つの領域は、子どもがバランスよく育つための視点です。
これをもとに支援の目標が立てられ、活動が設計されています。
発達に偏りがある子どもでも、得意なところを伸ばし、苦手なところを支援できる枠組みです。
理解することで支援内容がより納得できる
5領域を理解しておくことで、施設で行われている支援の意味や目的が見えやすくなります。
「この活動は何の力を育てるものなのか」がわかると、支援への信頼感も高まります。
保護者としても、成長を実感しやすくなります。
納得できる支援は、子どもにとっても大きな安心になります。
保護者と支援者が協力するための共通言語になる
5領域は、保護者と支援者が同じ方向を向いて子どもを支えるための「共通言語」となります。
それぞれの立場でできる支援を考え、連携して取り組むことで、子どもの可能性はどんどん広がっていきます。
5領域をうまく活用して、家庭と施設が協力し合う関係を築いていきましょう。
この記事が、子どもの成長を応援するためのヒントとなれば幸いです。
放課後等デイサービスの起業は療育ネットにお任せください
今回この記事では、放課後等デイサービスの5領域について解説いたしましたが、この記事を機に、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスの提供や福祉業界への新規参入を検討している方もいらっしゃるかと思います。
療育事業の開業支援は、私たち療育ネットにお任せください!
療育ネットでは、オーナー様のお考えを第一に、お一人ずつに合った開業方法をご提案いたします。
障害や特性により社会における生きづらさを感じている子どもたちが、「今」置かれている環境に悲観して自ら選択肢を閉ざすことなく自分らしく未来を生きていけるよう、乳幼児期からの関わりを大切に、療育事業を展開しております。
また、成人後も地域での暮らしや就労を通して、自己実現できるよう、必要な社会資源の創出を行います。
全国で324件の開業支援実績があり、安心してご依頼いただけます。
また、この制度を理解することは難しく、開業の伴走支援型の弊社サービスが役立つので、ぜひご相談ください。
ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。