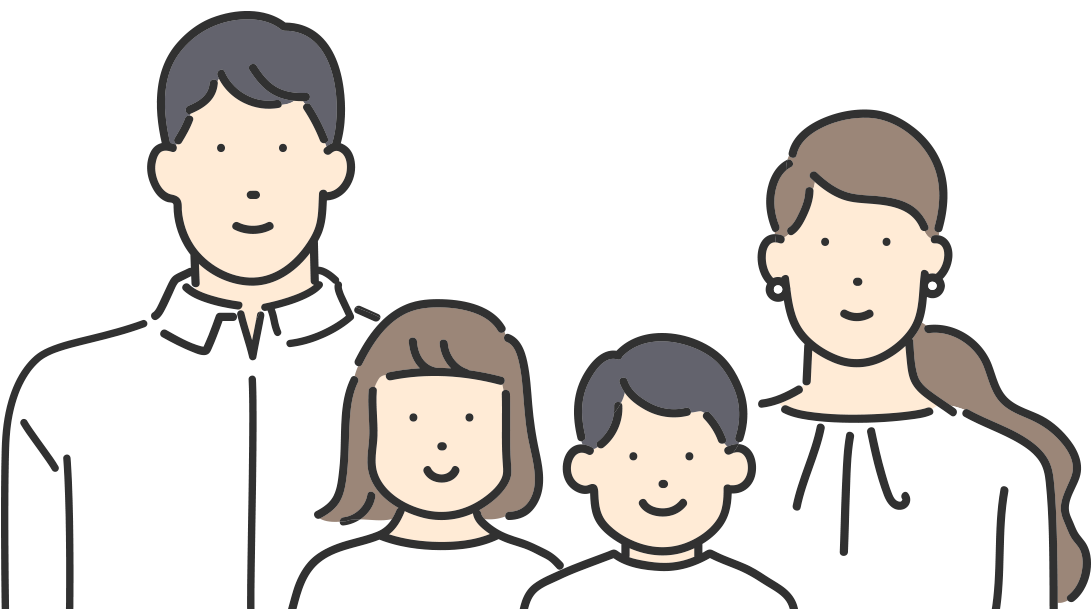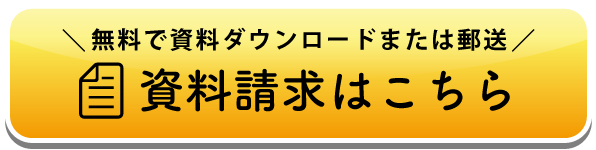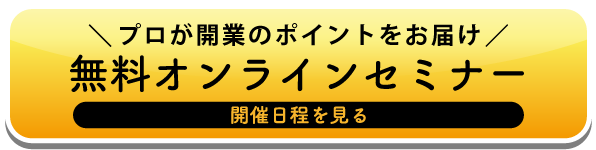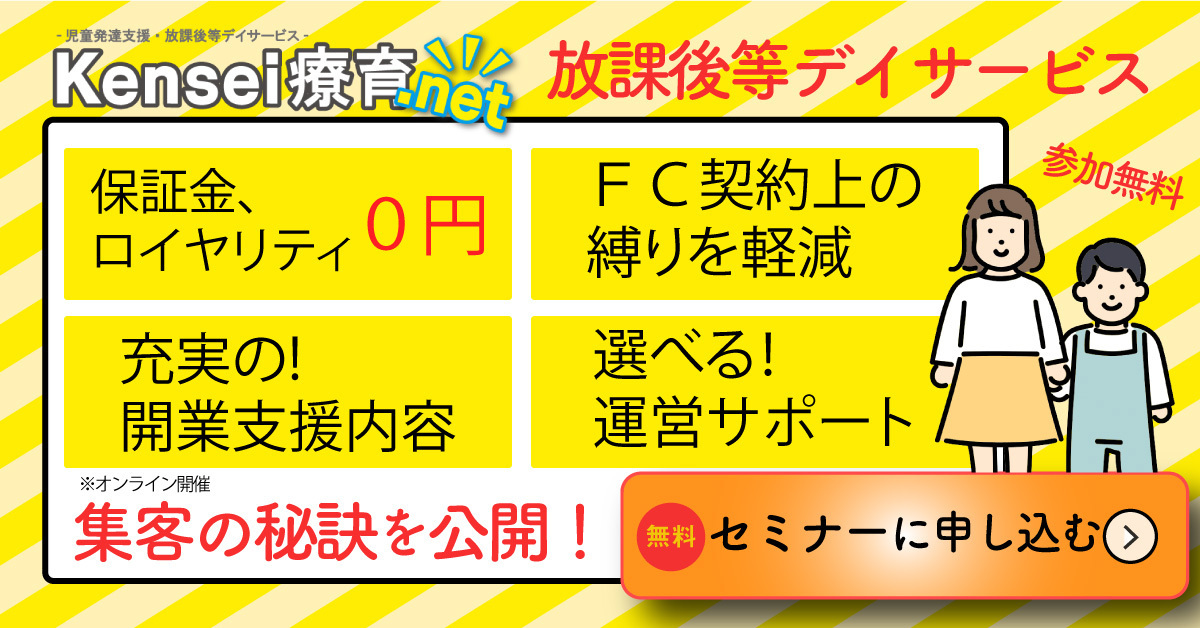【2024年度対応】放課後等デイサービスにおける延長支援加算の制度内容と算定要件をわかりやすく解説

放課後等デイサービスにおける「延長支援加算」は、平日3時間・学校休業日5時間という最長の時間区分を超えて、預かりニーズに対応した支援を計画的に行った場合に算定できる加算です。また、児童発達支援については、 平日・学校休業日ともに5時間を超える支援に対して算定できる加算となります。2024年度の障害福祉サービス等報酬改定では、延長の算定方法・必要体制・単位数が明確化されました。この記事では、制度の目的・要件・計算方法・注意点をやさしく解説します。
放課後等デイサービスにおける延長支援加算とは?基本的な仕組みを解説
この章では延長支援加算の概要と、支援時間に応じた評価の考え方を解説します。
延長支援加算は「最長時間区分を超えた」預かり支援を評価
放課後等デイサービスは、平日は支援時間の最長が3時間、学校休業日は5時間、児童発達支援については前述のとおり、 支援時間の最長が平日・学校休業日ともに5時間です。この最長時間区分を超えて、個別支援計画に基づき前後に預かり支援を実施した場合に延長支援加算を算定できます。延長の判断は「18時以降」といった時刻ではなく、所要時間を基準に行います。
家庭事情に応じた柔軟な支援
共働きやひとり親、疾病・通院、学校の下校時間などにより迎えが遅くなる場合でも、子どもが安全に過ごせる環境を確保するための仕組みです。延長の必要性は個別支援計画で位置付け、実績記録で裏づけます。
届出(体制届)は必要/「認可」は不要
延長支援加算の算定に当たっては、自治体の要領に沿って体制等に関する届出(体制届)を提出します。様式は自治体ごとに異なります。
放課後等デイサービスにおける延長支援加算が導入された背景と目的
共働き世帯の増加で預かりニーズが拡大
総務省「労働力調査(詳細集計)」の2023年平均では、共働き世帯が専業主婦世帯を大きく上回っています。就労等により迎えが遅くなる家庭に対応するため、発達支援後の預かり時間を評価する仕組みが整えられました。
障害のある子どもの安心と継続支援
環境変化に敏感な子どもが、慣れた場所で安心して過ごせる時間を確保することは重要です。個別支援計画に沿って、延長時間帯も安全・継続的な支援を提供できる体制が求められます。
放課後等デイサービスの延長支援加算の最新制度改正ポイント(2024年度)

最長時間区分の創設と延長評価
基本報酬に支援時間の区分(放デイ:時間区分1=30分超~1.5時間、2=1.5~3時間、3=3~5時間)が創設され、最長時間区分(平日3時間・休業日5時間)を超えた預かり支援を延長支援加算で評価します。
また、児童発達支援については前述のとおり、 支援時間の最長が平日・学校休業日ともに5時間を超えた預かり支援を延長支援加算で評価します。
個別支援計画への時間の明記(30分以上)
標準的な支援時間を個別支援計画に位置づけ(30分以上)、その前後で行う預かり支援を計画的に実施します。モニタリングにより定期見直しを行い、実績と計画の整合も確認します。
延長時間帯の職員体制
延長時間帯は職員2名以上(うち1名は人員基準により置くべき職員。児童発達支援管理責任者の対応も可)の配置が必要です。
ただし、延長支援がサービス提供時間内である場合は、通常の基準人員配置を行っていないと欠如になるので注意。
単位数(1日あたり)の明確化
- 障害児:延長30分以上1時間未満(30分以上~1時間未満(61単位)が算定できるのは、利用者都合により実際の延長支援時間が1時間未満となった場合のみ)=61単位、1~2時間未満=92単位、2時間以上=123単位
- 重症心身障害児・医療的ケア児:同128/192/256
※主として重症心身障害児を通わせる事業所で基本報酬に時間区分を導入しないケースは従前の扱い。
放課後等デイサービスの延長支援加算の対象となる子ども
保護者の就労・疾病等で迎えが遅くなる子ども
フルタイム勤務や通院等で迎えが遅くなる場合など、延長支援の申し出が可能です。
下校時間が遅い特別支援学校の児童
下校時刻の関係で最長時間区分を超える場合、学校予定等に基づき合理的な延長時間を設定します。
医療的ケア児等、長時間の見守りが必要な児童
人工呼吸器管理、吸引、経管栄養など日常的ケアが必要な児童では、長時間の安全確保のため延長が必要となる場合があります。対応体制(看護職等)を整え、計画・記録に具体的に反映します。
放課後等デイサービスの延長支援加算の算定要件

- 最長時間区分(平日3h/休業日5h)を超える時間に預かり支援を提供していること
- 個別支援計画に延長の理由と時間を明記し、計画的に実施していること
- 体制届の提出(自治体要領に従う)
- 職員2名以上(うち1名は人員基準による職員、児発管可)の延長時間帯配置
- 実施記録(時間・内容・職員体制等)を整備し、5年間保存(基準省令)
※送迎時間は延長時間に含みません。 - 営業時間が6時間以上であること
算定方法と計算例
単位数の把握
- 障害児:61/92/123 単位
- 重症・医ケア児:128/192/256 単位
(いずれも 30分以上1時間未満/1~2時間未満/2時間以上)
請求金額の算出
加算単位数 × 地域単価(1単位=10円が基本、地域区分により10.0~約11.2円)
《例》障害児で1~2時間未満(92単位)を月12日提供、地域単価10.0円の場合
92 × 12 × 10.0円 = 11,040円/月(延長支援加算分)
《例》重症・医ケア児で2時間以上(256単位)を10日、地域単価10.0円の場合
256 × 10 × 10.0円 = 25,600円/月
請求時の注意点
- 計画と実績の整合:個別支援計画へ定めた支援時間(最長の時間区分⇒3~5時間)を当日の実績と照らし合わせる
- 記録の整備:開始・終了時刻、内容、職員配置、対象時等の記録を5年保存。
- 届出・様式:体制届は自治体要領どおりに。
他の加算との違いと延長支援加算の位置づけ
延長支援加算は預かりニーズへの対応を評価する加算です。支援内容や専門体制を評価する他加算とは目的が異なります。家庭事情や学校の時間割など、外的要因に左右されやすいため、個別支援計画書別表への詳細な記載と、ミスや漏れの無い実績記録の作成が重要です。
まとめ

放課後等デイサービスの延長支援加算は、就労家庭や医療的ケア児など長時間の見守りが必要な子どもと家族を支える重要な制度です。2024年度改定で評価区分・体制・単位数が明確化され、個別支援計画(最長時間区分での設定及び延長の理由・時間の設定)・職員2名体制・記録5年保存など、実務の要点が整理されました。制度を正しく活用し、子どもと家庭の安心・安全な暮らしを支えましょう。迷う場合は、管轄自治体へ事前相談することをおすすめします。
放課後等デイサービスの起業は療育ネットにお任せください
今回この記事では、放課後等デイサービスの延長支援加算について解説いたしましたが、この記事を機に、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスの提供や福祉業界への新規参入を検討している方もいらっしゃるかと思います。 療育事業の開業支援は、私たち療育ネットにお任せください! 療育ネットでは、オーナー様のお考えを第一に、お一人ずつに合った開業方法をご提案いたします。 障害や特性により社会における生きづらさを感じている子どもたちが、「今」置かれている環境に悲観して自ら選択肢を閉ざすことなく自分らしく未来を生きていけるよう、乳幼児期からの関わりを大切に、療育事業を展開しております。 また、成人後も地域での暮らしや就労を通して、自己実現できるよう、必要な社会資源の創出を行います。全国で402件の開業支援実績があり、安心してご依頼いただけます。ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。