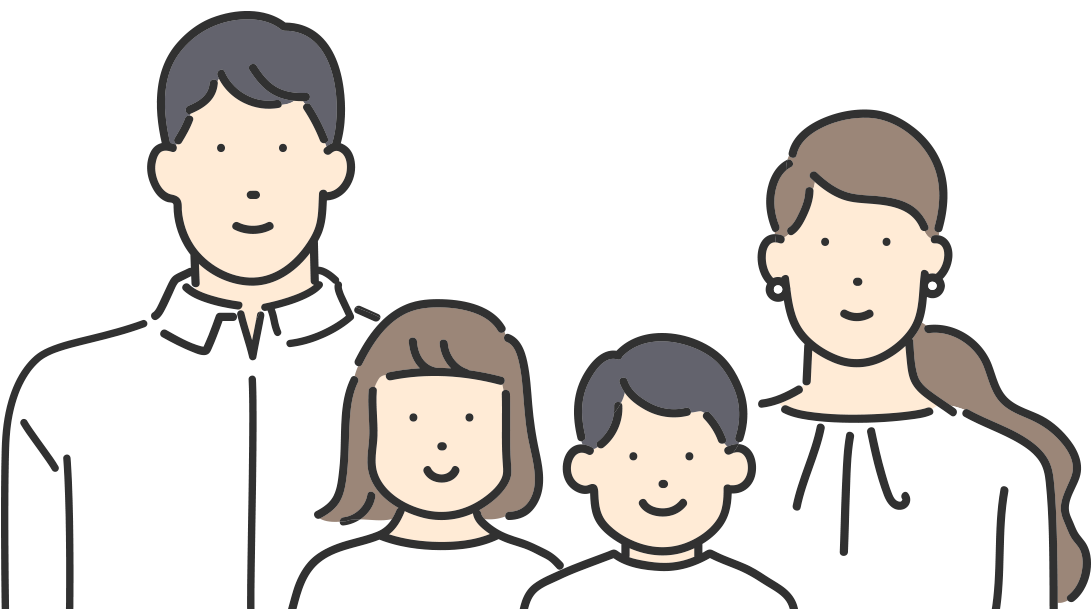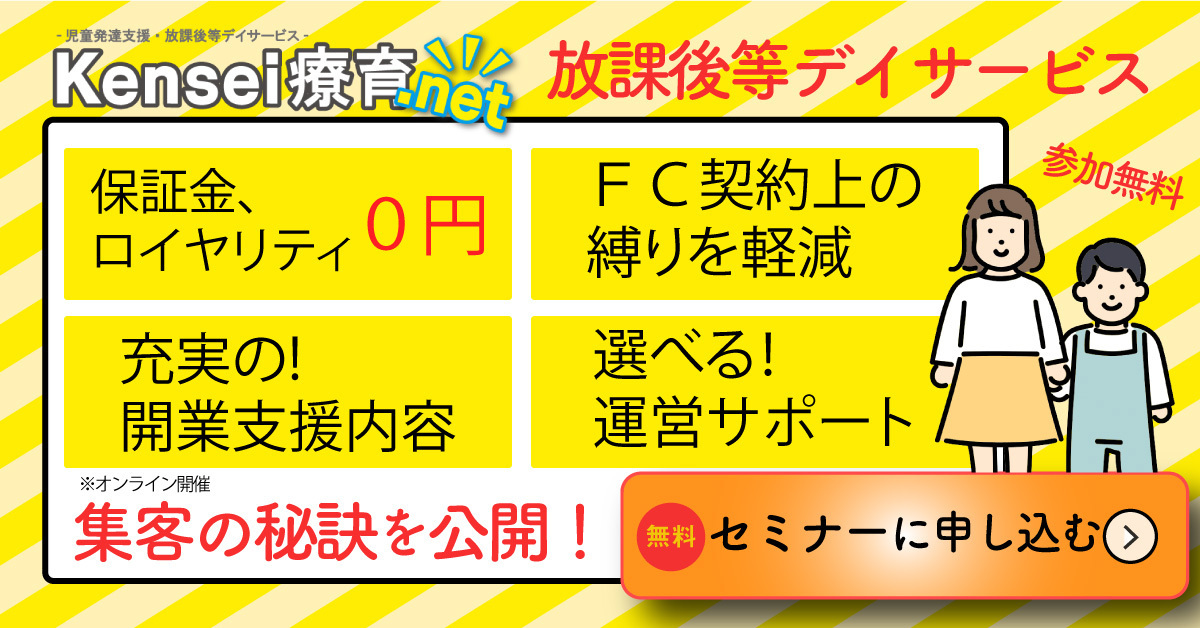【2025年最新版】放課後等デイサービスの利用者数の推移と背景・課題を徹底解説


放課後等デイサービスは、障害や発達に特性のある子どもたちが放課後や休日に安心して過ごせる場所として、全国でその重要性が高まっています。2012年の制度創設以降、利用者数は増加の一途をたどり、現在では30万人を超える子どもたちが利用しています。
本記事では、厚生労働省や政府統計など信頼できるデータをもとに、放課後等デイサービスの利用者数の推移などを詳しく解説します。
制度の正しい理解と、保護者・支援者にとって必要な情報をわかりやすく整理していますので、ぜひ参考にしてください。
放課後等デイサービスの利用者数の推移とは?
この章では、制度が始まった2012年から2025年までの放課後等デイサービス利用者数の推移と特徴的な動きについてまとめます。
2012年の制度創設以降、右肩上がりに増加している
放課後等デイサービスは、2012年の児童福祉法改正により「障害児通所支援」の一つとして創設されました。当初は約5万人の利用者数でしたが、制度創設期から利用者は年々増加しており、直近では約37.5万人(令和7年1〜3月の平均:375,211人)まで拡大しています。
この増加は、障害のある子どもに対する支援の必要性が広く認識されるようになったことや、制度として安定してきたことが大きく影響しています。
特に2016年〜2020年の間に事業所数が飛躍的に増えたことで、地域でのアクセスが大きく改善されました。
このように、制度創設から10年以上が経過し、放課後等デイサービスは福祉サービスとして社会に根付いたと言えます。
2020年以降の増加率はやや鈍化傾向にある
2012年から2019年までの間、利用者数は年平均20%前後の高い伸び率を記録していました。一方、近年は増加ペースが緩やかになっています。
背景には、一定数の需要がすでにサービスに取り込まれたこと、制度の安定化による成長の鈍化、またコロナ禍による一時的な利用控えも影響したと考えられます。
ただし、成長が鈍化したとはいえ、依然としてニーズは高く、新規利用者は着実に増加しています。
今後は、単なる量的拡大ではなく、「質の向上」や「対象児童の特性に合った支援」が求められるフェーズに移行しています。
放課後等デイサービスの利用者数が増加している背景

ここでは、なぜ放課後等デイサービスの利用者がこれほどまでに増加しているのか、その社会的背景を見ていきます。
発達障害の認知度が高まり診断数が増えたから
発達障害という言葉は近年メディアでも多く取り上げられ、社会的な認知度が大きく高まりました。その結果、発達障害の特性を持つ子どもが早期に見つかり、医師の診断や支援につながるケースが増えています。
早期療育や教育支援が重要視される中で、放課後等デイサービスはその受け皿として期待されています。
このように、利用者数の増加は社会の理解の進展と密接に関わっています。
共働き世帯の増加で放課後の支援ニーズが高まっているから
共働き世帯の割合は年々増加しています。共働き家庭では、学校終了後に家庭でのケアが難しいことが多く、安心して子どもを預けられる場所として放課後等デイサービスが選ばれています。
また、障害児の場合は一般の学童保育の受け入れが難しい場合もあるため、より専門的な支援が可能な放課後等デイサービスの利用が進んでいます。
保護者にとって、送迎対応や個別支援が受けられる放課後等デイサービスは、子どもの安心と家庭の生活の両立を支える重要な存在となっています。
こうした社会的背景も、利用者数の増加に影響しています。
放課後等デイサービス事業所数が急増しているから
サービスの拡充とともに、事業所数も大きく増加しています。令和7年1〜3月の平均で全国の事業所数は22,748カ所にのぼります。
事業所数が増えたことで、地域ごとの選択肢が広がり、通所しやすい環境が整備されつつあります。
一方で、急激な増加は質の確保にも課題を生じており、この点については後述します。
しかし、利用者数増加の一因として、物理的に通える場所が増えたことは明らかです。
放課後等デイサービスの利用者数の推移から見える課題

利用者数が増加する一方で、制度上・運用上のさまざまな課題も浮かび上がっています。ここでは代表的な課題を紹介します。
質の低い事業所の乱立が課題となっている
事業所数の増加に伴い、人員配置や支援内容に問題のある事業所の存在が懸念されています。厚生労働省の監査結果では、一部で基準未達や不適切な運営が報告されました。
特に、報酬を得るためだけの形式的な支援や、保育・療育の専門性が不足しているケースが問題視されています。
2024年(令和6年度)の報酬改定では、加算の見直しや人材基準の強化など、質の向上を目的とした制度改革が進められています。
今後は、「選ばれる事業所」になるための支援の質が求められるようになるでしょう。
一部地域で定員オーバーや送迎不足が発生している
都市部を中心に、利用希望者が定員を大幅に上回るケースが増えています。特に東京都・大阪府など人口密集地域では、空きがないために利用できない家庭もあるとされています。
また、送迎サービスを提供する事業所が多い中で、ドライバー不足や車両台数の制限により、「送迎エリア外」で利用が難しいという声もあります。
こうした問題に対しては、地域ごとの支援体制の拡充や、行政と連携したマッチング体制の強化が必要です。
今後、地域格差を解消する政策が求められます。
障害種別ごとの放課後等デイサービス利用者数の推移
障害種別によっても放課後等デイサービスの利用傾向は異なります。
自閉スペクトラム症の子どもの利用が最も多い
一部の自治体や研究機関の報告では、自閉スペクトラム症(ASD)の子どもの利用が最も多い傾向にあるとされています。
ただし、全国集計で障害種別別の利用構成を網羅的に示す最新の公的統計は限定的であり、全国一律に「最も多い」とは断定できません。
自閉スペクトラム症の子どもは、集団適応やコミュニケーションに特性があることから、個別支援を受けやすい環境を求める傾向があります。
事業所側でもASD支援の専門スタッフを配置するケースが増えており、社会性トレーニングや感覚統合を取り入れた支援など、個別ニーズに対応した取り組みが進んでいます。
今後もこの層の支援充実がサービスの質を左右するポイントになるでしょう。
知的障害児の利用数も増加傾向にある
知的障害児の利用も年々増加しています。特に中度の知的障害を持つ子どもの利用が多く、生活スキル訓練や集団活動を通じた自立支援が重視されています。
学校教育では対応しきれない部分を補う機能として、放課後等デイサービスが重要な役割を果たしています。
こうした支援を受けることで、将来的な就労支援や地域生活への移行にも好影響が見られています。
知的障害児支援の充実は、地域の包摂社会づくりにもつながっています。
2025年の放課後等デイサービス利用者数推移の最新データ
ここでは、厚生労働省の令和6年度データをもとに、2025年時点での最新統計をまとめます。
2025年4月時点で約31万人が利用
厚労省が公表した「障害福祉サービス等の利用状況」によると、直近公表(令和7年1〜3月平均)の放課後等デイサービス利用者数は約37.5万人となっています。
これは前年に比べての増加傾向が続いていることを示しています。
この数字は、全国の障害児通所支援を受けている児童の中でこどもの利用者が多数を占めていることを示しています。需要の高さに対して、質的な改善をどう図るかが次の焦点です。
事業所数は全国で約20,000カ所に達している
2025年現在、全国の事業所数は令和7年1〜3月平均で22,748カ所に到達しました。
都市部では選択肢が多い一方で、地方では未整備地域も残っており、地域差が課題です。
国や自治体は、通所体制の確保や質の向上に向けた取組を進めています。
令和6年度報酬改定により質の向上が期待されている
令和6年度の障害福祉サービス報酬改定では、放課後等デイサービスに関して個別支援計画の質向上、専門職配置の加算強化が行われました。
この改定により、専門的支援を提供する事業所の報酬が上がり、質の高い支援が促される仕組みになっています。
また、支援の実績や保護者との連携を重視する評価項目も新設され、より透明性の高い運営が求められています。
量の拡大から質の向上へ──放課後等デイサービスは今、転換期を迎えています。
放課後等デイサービスの利用者数推移から考える支援のあり方

利用者数の増加から見える課題を踏まえ、今後の放課後等デイサービスのあり方について考察します。
重度障害児向けの専門的な支援体制が必要
重度障害児の受け入れが難しい現状を改善するためには、医療的ケア児対応加算の強化や専門職の常駐化が不可欠です。
看護師・理学療法士・言語聴覚士などの多職種連携を推進し、支援の幅を広げる取り組みが求められます。
重度児を対象とした施設の整備や専門人材の育成が進むことで、真にすべての子どもが利用できる仕組みへと近づくでしょう。
「どんな障害があっても安心して通える」社会の実現が目標です。
地域格差を是正する支援モデルの構築が急務
地方と都市部の格差を縮めるため、国や自治体は連携して「地域支援モデル」の構築を進める必要があります。
具体的には、自治体間での事業所ネットワーク化やICT活用支援が有効です。
また、地域の医療機関・学校・行政が連携して情報共有を進める仕組みづくりが求められています。
地域ごとに異なる課題に応じた支援体制の柔軟な運用が、今後の鍵になります。
利用者と事業所をマッチングする仕組みが求められる
現在、利用希望者がどの事業所に空きがあるかを把握しづらいという課題があります。
これを解決するために、オンライン上で利用状況や支援内容を可視化するマッチングシステムの整備が検討されています。
自治体単位での情報共有が進むことで、より効率的な利用が可能になります。
支援ニーズと事業所の特性を適切に結びつけることが、今後の利用者満足度を高めるカギです。
まとめ|放課後等デイサービスの利用者数推移と今後の展望
ここまで、放課後等デイサービスの利用者数の推移とその背景、今後の方向性について解説しました。
利用者数は今後も増加傾向が続くと予測される
2025年現在、全国で約37.5万人が利用しており、今後も増加が続く見込みです。
制度の成熟に合わせた改革が求められます。
質の確保と重度児支援の強化が今後のカギ
報酬改定や監査体制の強化を通じて、質の高い支援を提供する事業所が評価される仕組みが進んでいます。
特に重度障害児や医療的ケア児を支える専門体制の強化が重要です。
全ての子どもにとって安心・安全な放課後の居場所を確保するための基盤づくりが、行政と地域の共通課題となります。
現場で働く支援者への教育・研修体制の充実も不可欠です。
地域ごとの支援体制の強化が重要になる
都市部と地方での格差をなくし、全国どこでも質の高い支援を受けられる体制が求められます。
国・自治体・民間事業者が連携して、地域に根ざした支援モデルの構築を進めることが必要です。
ICTの活用や人材育成を通じて、地域に最適な形で支援を届ける取り組みが期待されます。
放課後等デイサービスは、これからの日本の福祉の姿を映す重要な存在です。
今後も正確なデータに基づき、利用者と支援者の双方がより良い関係を築ける制度の発展が望まれます。
放課後等デイサービスの起業は療育ネットにお任せください
この記事を機に、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスの提供や福祉業界への新規参入を検討している方もいらっしゃるかと思います。
療育事業の開業支援は、私たち療育ネットにお任せください!
療育ネットでは、オーナー様のお考えを第一に、お一人ずつに合った開業方法をご提案いたします。
障害や特性により社会における生きづらさを感じている子どもたちが、「今」置かれている環境に悲観して自ら選択肢を閉ざすことなく自分らしく未来を生きていけるよう、乳幼児期からの関わりを大切に、療育事業を展開しております。
また、成人後も地域での暮らしや就労を通して、自己実現できるよう、必要な社会資源の創出を行います。
全国で400件を超える支援実績があり、安心してご依頼いただけます。ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから