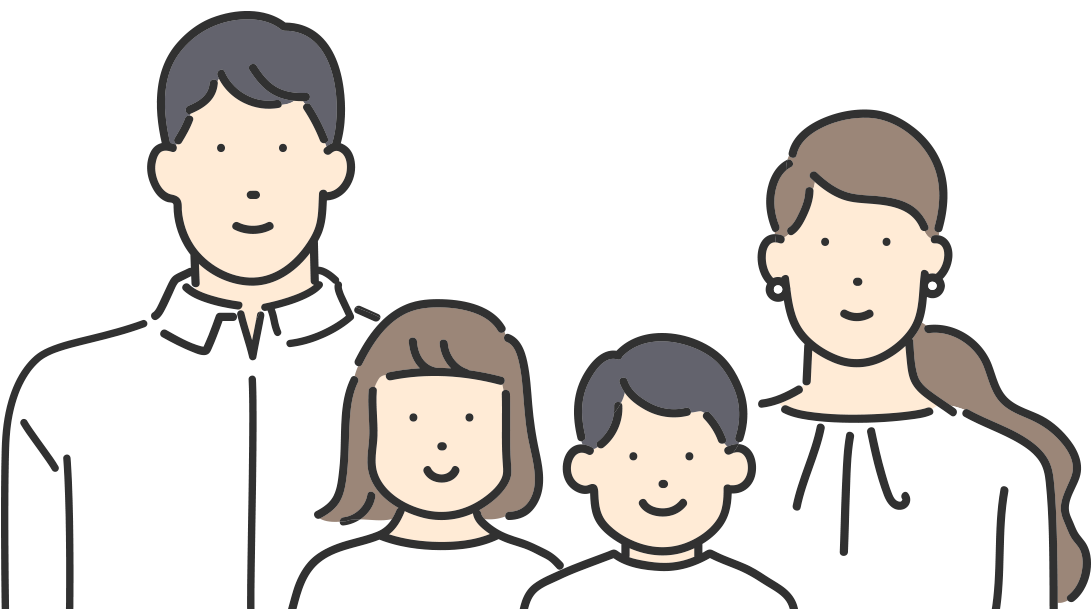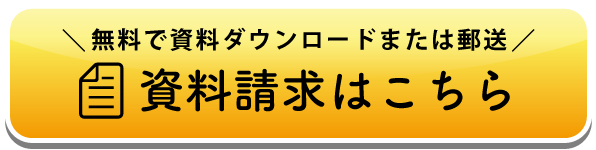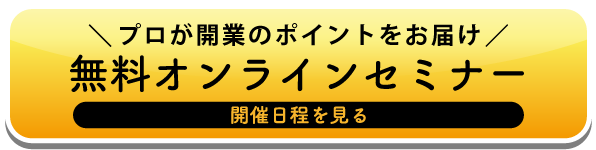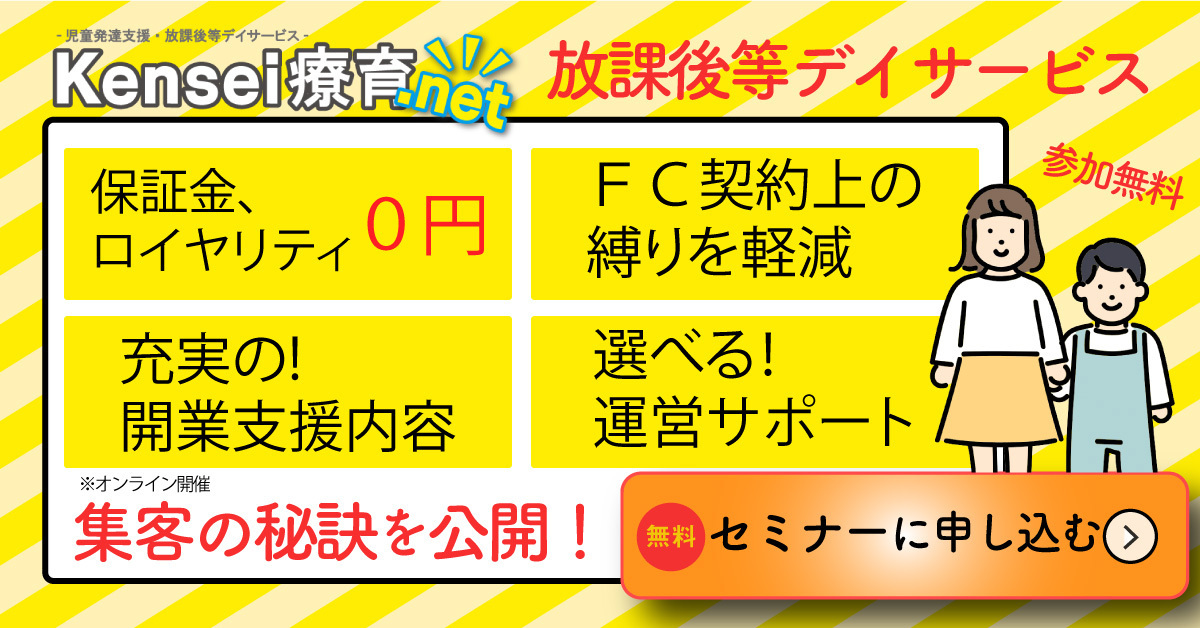「障害児福祉手当」とは?対象や注意したいポイントをわかりやすく解説!所得制限
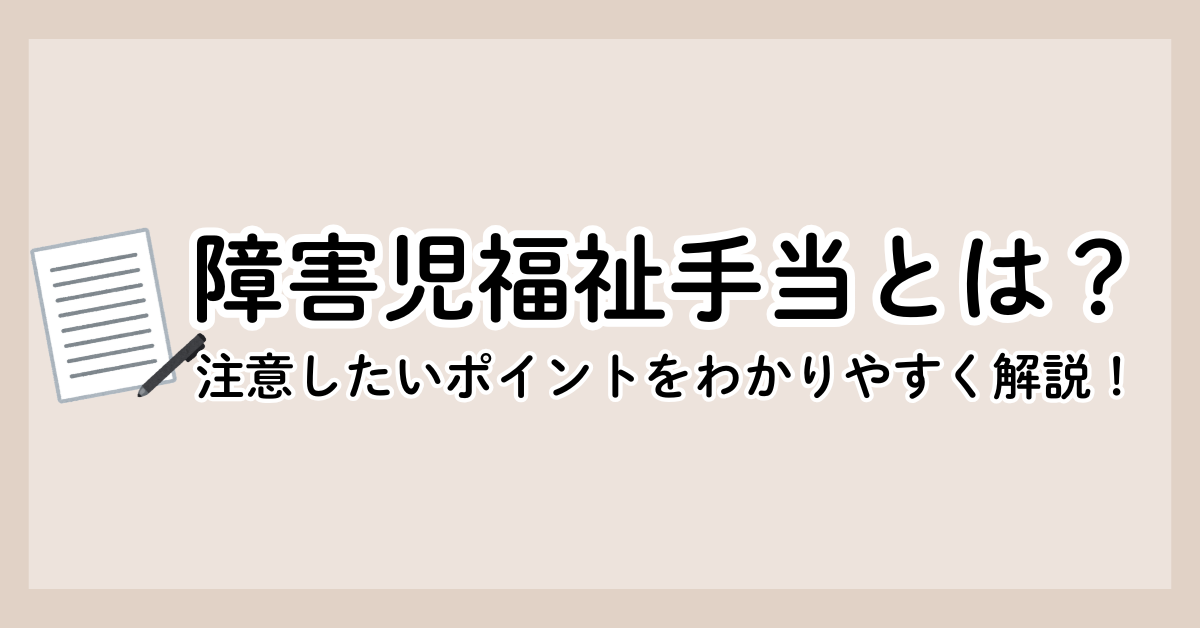
「障害児福祉手当」とは?
障害のあるお子さんを育てているご家庭にとって、日々の介護や見守りには多くのエネルギーが必要です。
そんなご家族を経済的に支援するための制度のひとつが「障害児福祉手当」です。
今回は、この手当の内容や対象者、申請方法、所得制限についても、わかりやすくご紹介します。
障害児福祉手当とは?
「障害児福祉手当」は、重度の障害を持つ20歳未満のお子さんに対して支給される手当です。
日常生活において、常に介助が必要な状態であることが条件となります。
この手当は、障害児本人に対して支給されるもので、本人、または配偶者や家族に対する所得制限があります。
あくまで、ご家庭での介護にかかる負担を少しでも軽減するための支援策なので、対象となるかしっかり確認していきましょう!
支給対象となるのは?
以下のような条件を満たすお子さんが対象となります。
-
20歳未満であること
-
次のいずれかに該当する重度の障害があること
・身体障害者手帳1級または2級に相当
・療育手帳で「最重度」または「重度」に該当
・重度の知的障害・精神障害がある場合も含まれる -
施設に入所していないこと
-
病院に継続して3か月以上入院していないこと
※障害児福祉手当の認定は、地方自治体で行います。具体的な判断は市区町村での審査により決まります。
手当の金額と支給時期
2024年度の支給額は、**月額15,220円(年額で182,640円)**です。
年に4回(2月・5月・8月・11月)に分けて支給されます。
所得制限について
障害児福祉手当には、申請者本人(お子さん)の所得だけでなく、その扶養義務者(通常は保護者)の所得にも制限があります。
この基準を超えると、その年の手当は「支給停止」となります。
所得の限度額(目安)
扶養親族の人数などによって変動しますが、主な目安は以下の通りです(2024年度)。
| 扶養親族の人数 | 扶養義務者の所得制限限度額(概算) |
|---|---|
| 0人 | 約 6,287,000円 |
| 1人 | 約 6,536,000円 |
| 2人 | 約 6,749,000円 |
| 3人 | 約 6,962,000円 |
※あくまで概算であり、控除額や収入の種類などによって異なる場合があります。
また、扶養義務者の所得だけでなく、障害児本人の所得が高い場合も支給停止の対象になります。
(▶障害児本人の所得についてはコチラ)
※所得制限の詳細や適用については、お住まいの市区町村の福祉窓口で
最新の情報を確認されることをお勧めします。

申請方法は?
申請は、お住まいの市区町村の役所や福祉事務所で行います。
提出された書類を審査し、市が(町村分は府が)認定の可否を決定します。
認定されると、申請された月の翌月分からの手当が支給されます。
必要な書類には以下のようなものがあります。
-
所定の申請書
-
診断書(指定様式)
-
障害者手帳(または療育手帳)
-
所得状況を確認できる書類(マイナンバーなど)
※申請から支給までには、審査期間があるため、数ヶ月かかる場合があります。
注意しておきたいポイント
-
すでに他の手当(特別児童扶養手当など)を受けている場合でも、併給できることがあります(ただし、同一の趣旨の手当については調整されることも)。
-
毎年の所得確認(現況届)が必要です。期限を過ぎると支給が止まる場合があります。
-
所得制限を超えた場合でも、「停止」状態として記録が残るため、翌年の所得が基準を下回れば支給が再開されることもあります。
- 手当を受けようとする人又は児童が日本に住んでいないときは手当を受けることができません。
まとめ
「障害児福祉手当」は、重度の障害のあるお子さんを育てるご家庭の負担を少しでも和らげるための大切な制度です。所得制限はあるものの、該当するかどうかはケースによって異なります。
まずはお住まいの自治体に相談し、正確な情報を得ることが大切です。
経済的支援を受けながら、少しでも安心できる子育て環境を整えていきましょう。
▶厚生労働省のページはこちら
障害児福祉手当について(厚生労働省)