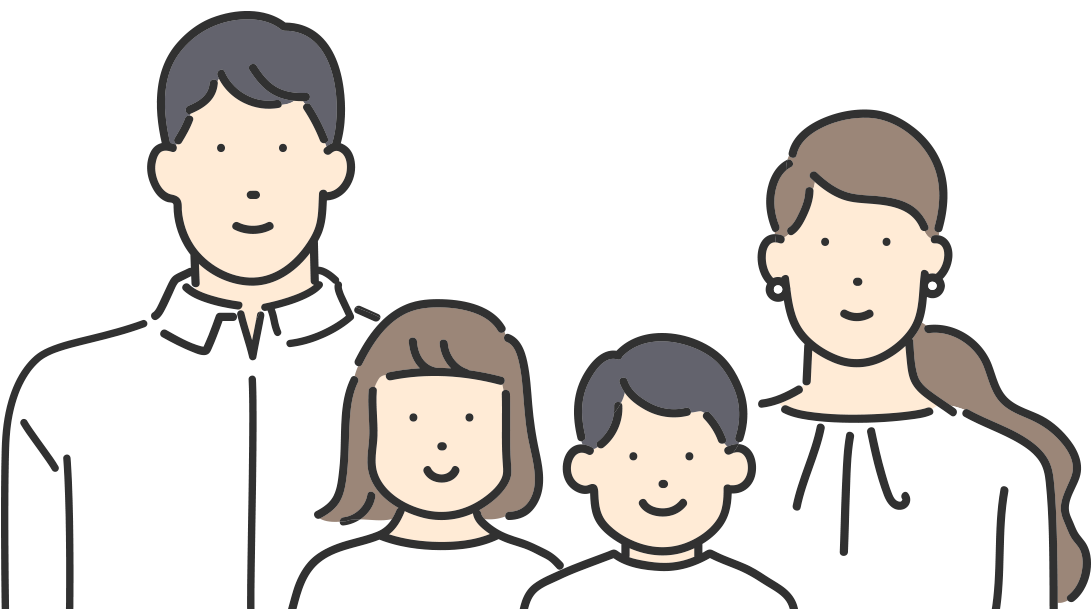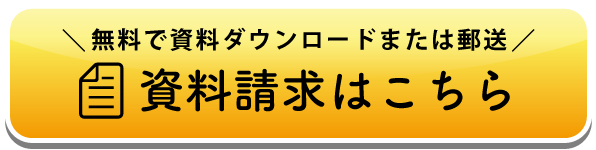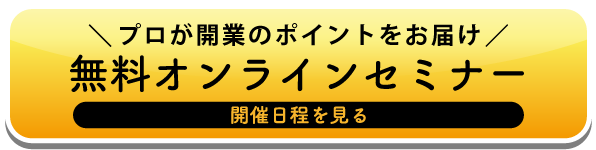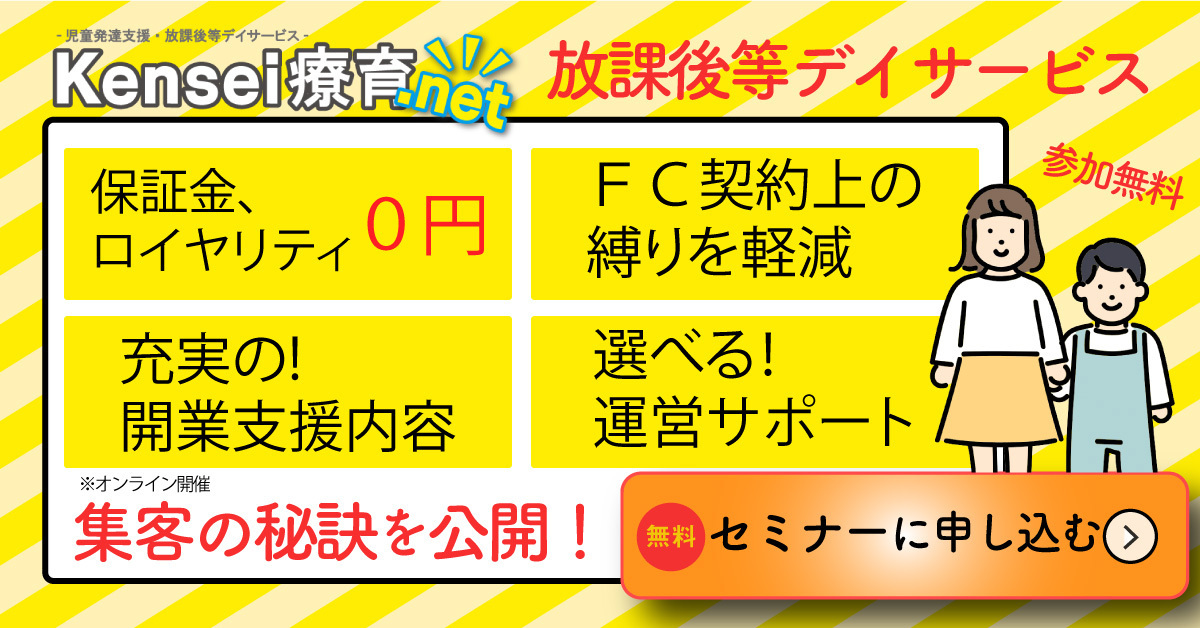放課後等デイサービスにおける上限管理の仕組みと流れをわかりやすく解説
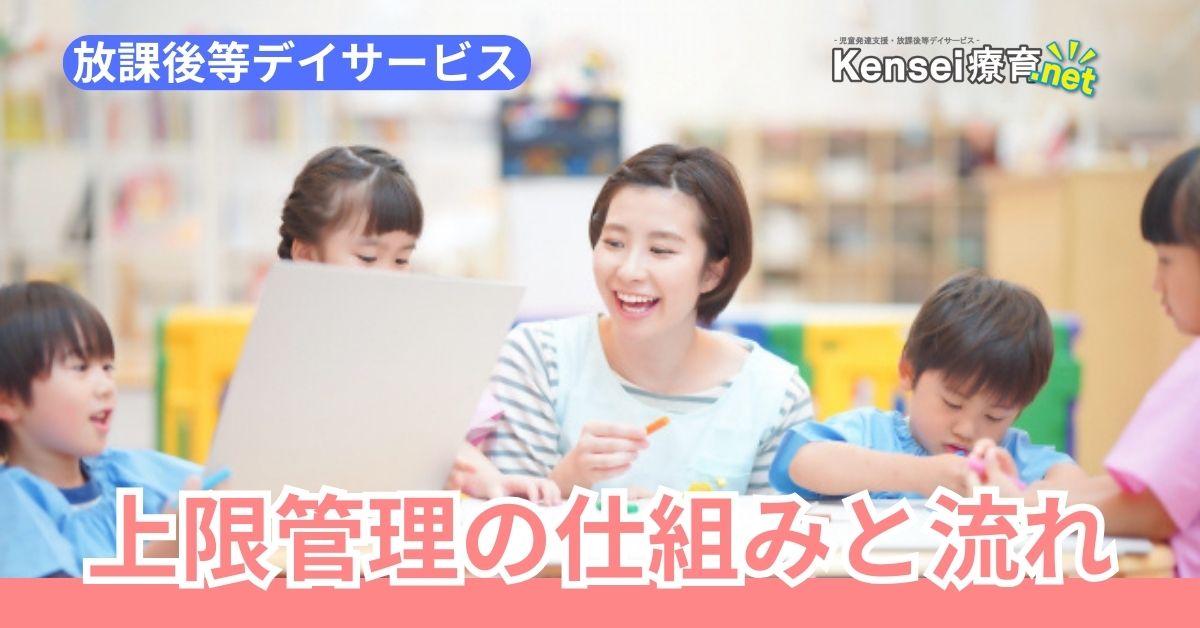
放課後等デイサービスを利用する際にたびたび出てくるであろう「上限管理」。
この記事では、上限管理の制度の仕組み、具体的な流れ、事業所が注意すべきポイントなどを解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
放課後等デイサービスにおける上限管理とは?
上限管理とは、利用者が複数の事業所を利用した場合に、保護者の自己負担額が一定の上限額を超えないように調整することで過度な自己負担を防ぎ、必要な支援を公平に受けられるようになる仕組みとなります。
こちらの仕組みは全国共通ですが、利用者一人ひとりの状況によって、適用内容に違いが生じることもあります。
そのため、事業所としては制度全体を理解しながらも、個別の状況に応じて対応することが大切です。
「上限管理」が発生する条件
上限管理の対象児童の要件としては、以下の内容が挙げられます。
〇利用者が複数の事業所との契約し、それぞれの事業所からの請求が発生する場合
複数の事業所を利用している場合、上限管理を行っていないと、それぞれの事業所からの請求が発生し、後述の「負担上限月額」を超えた金額を保護者は負担しなければならなくなります。
〇受給者証の「負担上限月額」の欄に、「4,600円」又は「37,200円」の記載がある場合
負担上限月額は利用者の世帯所得に準じて、以下のように分類されます。
・非課税世帯:0円
・課税世帯(年収概ね890万円以下):月額4,600円
・課税世帯(年収概ね890万円以上):月額37,200円
月々の上限額が決まっている為、この金額以上の負担が発生しない、という金額となっていますが、こちらが上限管理の要件の1つでもあります。※0円の場合は複数事業所を利用していても、上限管理は発生しません。(管理する金額がそもそも無い為)
上限管理の流れ
具体的にどういった流れで上限管理が進んでいくのかを見てみましょう。
①上限管理対象児童かの見極め
利用契約時、又は利用開始後に保護者から他の事業所との利用契約をしている(した)、というお話があったタイミングで、先述の2つの条件を満たしている場合、事業所は「上限管理事業所」を決めていきます。
※「上限管理事業所」は、利用者が複数事業所を利用している場合、上限額の管理を行う役割を持ちます。
基本的には1月の利用日数が1番多い事業所が上限管理事業所となる事が多いですが、保護者が事業所を指名の上で決まる事もあります。
事業所間での電話連絡等で決定する事も多いため、話があった際は併用事業所様へ連絡を入れるなどの対応を行いましょう。
②書類の提出
上限管理を開始するためには、原則、保護者が受給者証を交付した市区町村に対して、「利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書」という書類の提出を行う事で管理が可能となります。(市区町村によっては、事業所が代理で提出して良い場合も)
この書類の提出は市区町村により提出期限・様式等に違いがあるため、事前に事業所側から実施地域の市区町村への確認を行っておき、保護者へ説明が出来ればスムーズな対応が可能となります。
上限管理の申請を行った後に受給者証に上限管理事業所の記載がされる為、そちらも確認しましょう。
③利用者負担額一覧表の送付・受領
②の対応が終了し、1カ月のサービス提供を行った翌月、上限管理事業所以外の事業所は、基本サービス提供翌月の3日までに「利用者負担額一覧表」の送付を行っていきます。
こちらの書類はサービス提供に伴い、それぞれの事業所での実績に応じ発生した費用がいくら発生したのかを報告する様式です。
上限管理事業所はこちらを確認し、④に進んでいきます。
④利用者負担上限額管理結果票の送付・受領
上限管理事業所は③で集めた利用者負担額一覧表を基に、「利用者負担上限額管理結果票」を作成、サービス提供翌月の7日までその他の事業所へ送付を行う必要があります。
こちらの書類は集めた各事業所が最終的に幾らを保護者に請求するのかを纏めた書類となり、この通りに各事業所が請求することで、世帯所得に応じた負担上限月額を守り、余計な負担を負わせる事が無くなります。
※月額4,600円の上限がある家庭で、実際に利用したサービスの合計が2万円分だったとしても、請求されるのは上限の4,600円までとなり、それ以上の金額は各都道府県の国保連・受給者証を交付した市区町村が負担します(公費)。
⑤国保連請求・保護者請求
④の内容を基に、国保連請求・保護者請求を行い、上限管理の処理は終了となります。
その他注意すべきポイント

これまでは上限管理の仕組み、流れについてご説明しましたが、その中での注意すべきポイントなどについてご説明いたします。
兄弟で同じ放課後等デイサービスを利用する場合
たとえば、負担上限月額4,600円の世帯の兄と弟が同じ放課後等デイサービスAを利用していおり、それぞれの請求額が
・兄:5,000円
・弟:5,000円
となった場合、それぞれ4,600円を請求するのではなく、2人の合算額10,000円から世帯の上限額4,600円を保護者は負担し、超過分はすべて公費でカバーされます。
これは兄弟それぞれが別の事業所を利用する場合も同様となるため、兄弟の併用状況を把握した上で上限管理・請求処理を行う必要があります。
世帯の収入が変化した場合の上限額の見直し
世帯収入が大きく変化した場合は、自治体に届け出を行うことで上限額が見直される場合があります。
たとえば、保護者の失職や転職、所得減少などがあった場合、新たな所得証明書を提出することで変更となる場合もあります。 ※実際の反映には一定の時間がかかることがあります。
変更後の上限額が反映される月から自己負担額が変わるため、新たな受給者証の発行がされた際、又は変更が確定すると分かった際に事前に情報をいただけるよう、保護者とも共有をしておきましょう。
まとめ|放課後等デイサービスにおける上限管理の仕組みと流れをわかりやすく解説
放課後等デイサービスにおける上限管理制度は、複数の事業所を利用させたいニーズを持つ保護者にとって、安心してサービスを利用するための重要な仕組みです。
事業所にとっても、受給者証の確認、他サービスとの併用状況の把握が不可欠です。
上限管理の仕組みを正しく理解し、安心・安全なサービス利用に役立てていきましょう。
放課後等デイサービスの起業は療育ネットにお任せください
療育事業の開業支援は、私たち療育ネットにお任せください!
療育ネットでは、オーナー様のお考えを第一に、お一人ずつに合った開業方法をご提案いたします。
障害や特性により社会における生きづらさを感じている子どもたちが、「今」置かれている環境に悲観して自ら選択肢を閉ざすことなく自分らしく未来を生きていけるよう、乳幼児期からの関わりを大切に、療育事業を展開しております。
また、成人後も地域での暮らしや就労を通して、自己実現できるよう、必要な社会資源の創出を行います。
全国で324件の開業支援実績があり、安心してご依頼いただけます。
ぜひ一度、下記リンクよりお問い合わせください。