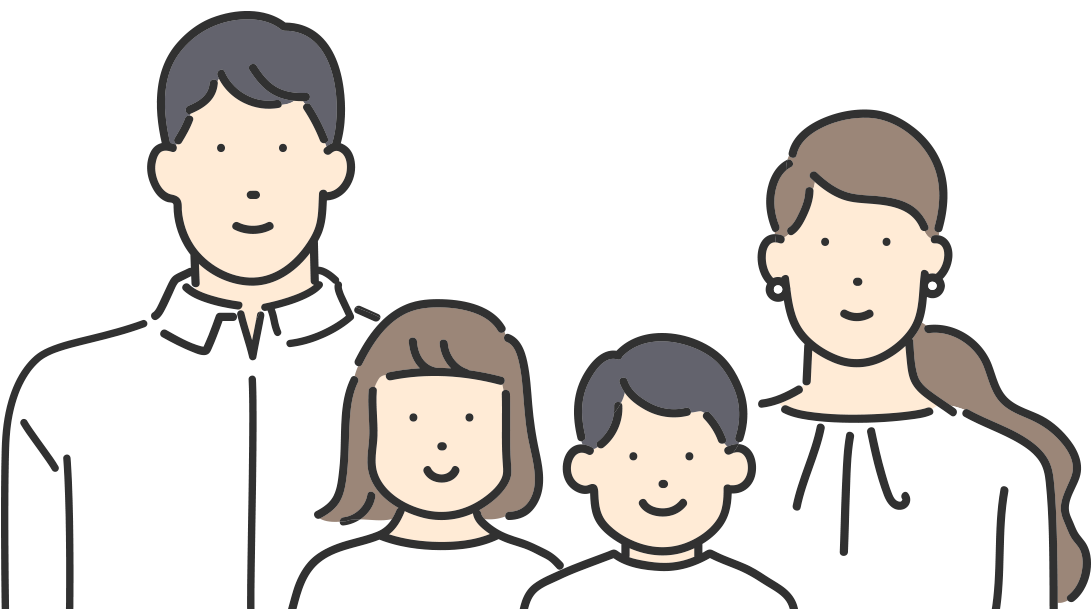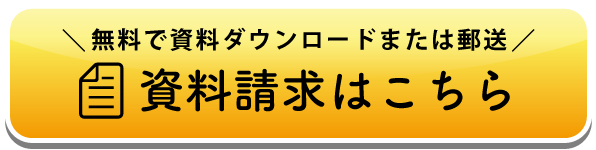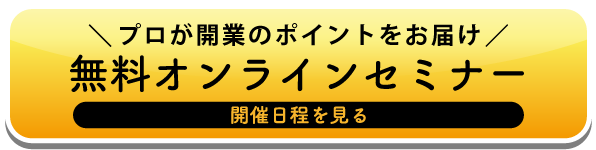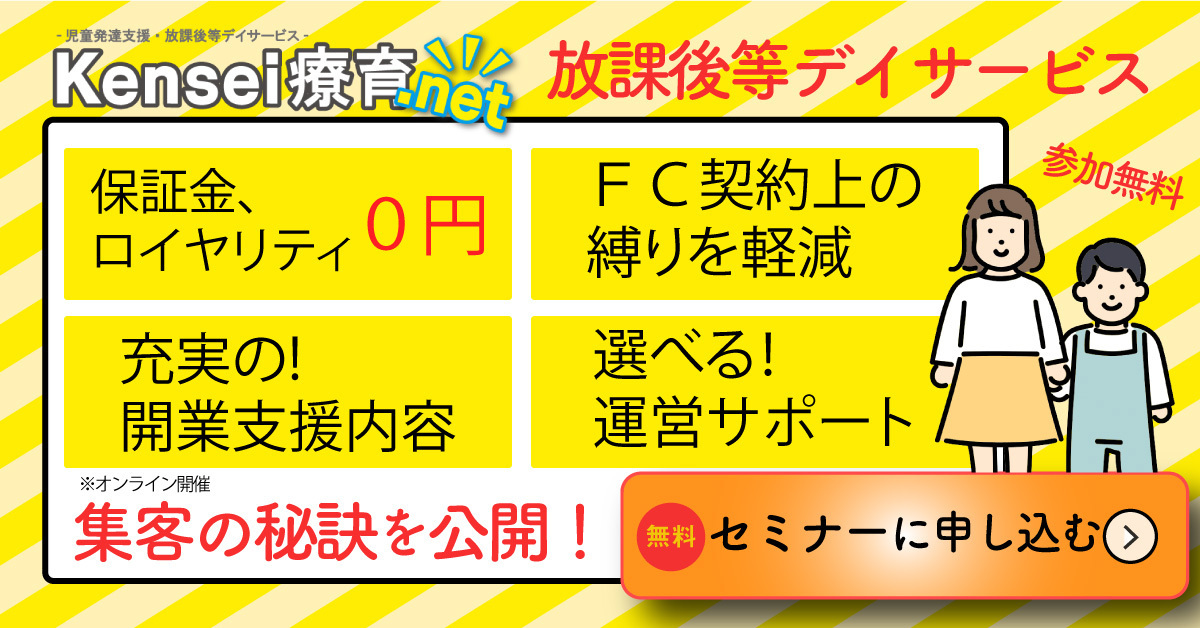【公式制度に基づく】放課後等デイサービスは18歳以上でも使える?特例制度の仕組みと手続き
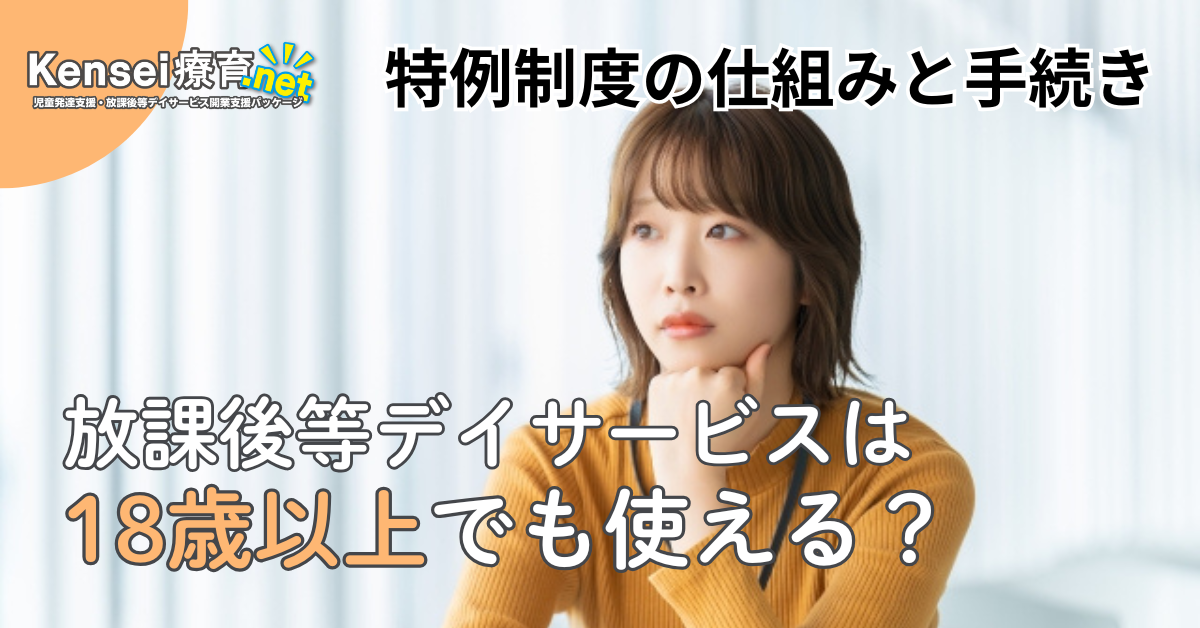
放課後等デイサービスは、障害のある児童が安心して放課後を過ごせる福祉サービスですが、「高校卒業後(18歳以上)も使えるのか?」と疑問に思う方も多いはずです。
結論から言えば、原則は「就学している障害児」が対象です(学校教育法第1条の学校⇒幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び 高等専門学校に就学)。卒業等で就学児ではなくなった後でも、厚生労働省の運用に基づく年齢の特例により、満20歳に達するまで利用継続が認められる場合があります。
この記事では、制度の出典に基づいた正確な情報をもとに、特例制度の仕組み・条件・申請方法・注意点をわかりやすく解説します。
放課後等デイサービスの特例(年齢の特例)制度を詳しく解説
「年齢の特例」とは?制度の背景
「年齢の特例」とは、就学児ではなくなった後も、必要性が認められると満20歳に達するまで放課後等デイサービスの利用を継続できる仕組みです。高等学校等の卒業後、直ちに一般就労や成人向け福祉サービスへ移行することが難しいケースに配慮し、連続性ある支援を確保するために位置づけられています。
制度上の位置づけは、厚生労働省の公式資料や運用解説に基づいて各自治体へ周知されており、市区町村が個別に支給決定します。
どのような場合に特例が検討されるのか?
以下のようなケースが一般的に検討対象となります(あくまで例示です)。
・障害特性や医療的ケア等の事情により、すぐに就労や成人向けサービスへ移れない場合
・家庭事情により、日中の居場所としての継続利用が当面必要な場合
・本人の発達状況や生活能力等の観点から、継続支援が妥当と判断される場合
判断・認定は自治体の個別審査
原則本人が申請し、市区町村が必要性を審査のうえ決定します。
申請時は申請書が必須で、医師の診断書等は「必要に応じて」求められます。学校や相談支援からの意見等は、自治体の求めに応じて提出します。詳細は自治体で異なるため、事前に確認しましょう。
18歳以上で利用するための条件・申請方法・必要書類
主な考え方(例)
・受給者証(通所受給者証)の有効期間が切れる前に申請すること
・次の進路・支援先が未整備で、短期的に継続支援が必要と認められること
・医師・学校・相談支援等の意見を踏まえ、市区町村が必要性を認めること
※ 具体的な要件は法令で一律に列挙されておらず、自治体の審査で総合判断されます。
申請の流れと提出先
- 本人からの継続利用に関する意思表示(相談支援専門員と協議)
- 市区町村の障害福祉担当へ申請書と添付資料を提出
- 審査・必要に応じヒアリング
- 認定結果に基づき受給者証の有効期間等が設定される(記載方法は自治体により異なる)
必要な書類の一例
・通所給付の支給申請書(様式は自治体)
・受給者証の写し
・医師の診断書等(必要に応じて)
・学校や相談支援等の意見書等(求めがある場合)
※ 何を求めるかは自治体の運用により異なります。
特例利用のメリットと注意点

生活リズムの維持
卒業直後の空白を避け、慣れた環境で支援を継続できるため、生活リズムの維持や不安軽減に役立ちます。
家庭の負担軽減
日中の居場所が確保され、保護者の就労継続や家庭負担の軽減につながります。
次の支援サービスへのスムーズな移行
生活スキルや社会性の維持・向上を図りつつ、生活介護・就労系など成人向けサービスへの移行準備が進めやすくなります。
注意点:特例はあくまで一時的
年齢の特例は満20歳到達までの一時的な継続です。期間内に成人向けサービスや住まい等の長期計画を、相談支援や関係機関と連携して進めましょう。
まとめ|特例で18歳以上も利用可能(満20歳まで)。就学継続なら原則対象
卒業後に就学児でなくなった場合でも、必要性が認められれば満20歳に達するまでの特例で継続可能です。
ただし、適用は自治体の個別審査によるため、本人の意思を第一として早めに談支援専門員や市区町村と連携し、必要書類を整えて申請を進めましょう。正しい制度理解と計画的な準備が、本人の安心・成長・自立につながります。
放課後等デイサービスの起業は療育ネットにお任せください
本記事を機に、放課後等デイサービスなど障害福祉サービスの提供や新規参入をご検討の方へ。
療育事業の開業支援は、私たち療育ネットにお任せください。オーナー様のお考えを第一に、お一人ずつに合った開業方法をご提案します。乳幼児期から成人期まで、地域での暮らし・就労につながる支援資源の創出にも取り組んでいます。全国で402件の開業支援実績。まずは下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。